スタッフ日記[2025]
[文 / 益田(制作)]
- 12/31

神田優花のニューシングル「Cobra」、本日発売です。 以下、アーティスト本人からのコメント。
Cobra/Love or Not
Cobra
ハイテンションでダンサブルな曲です。
ちぢこまらないようレコーディングに臨もうとは思っていたんですが、ふたを開けてみたら私の想定をかなり超えてきた曲です。
いつも歌を組み立てる時、ある程度の設計図を描いてその完成図に向かって仕上げていく感じなんですが、このこ(曲)はホント勝手に動きまくっていってしまいました。自分で歌ってるんですけど。
あれ?なんでこうなった?というくらいレコーディング時の記憶が、、、いやあるにはあるんですが、気がついたら録り終わっちゃってました。
思わず、今のでOK?って聞いてしまいました。
めったにない経験が出来て、楽しかったなぁ。
Love or Not
こちらはうって変わって、繊細で美しい曲です。
壊れやすいものを、そっと掬い上げる、そんな風に意識して歌っています。
抑えた表現の中の、言葉にならない瞬間を歌おうと取り組んだ1曲です。
ぜひ、聴いてみてください。
神田優花
- 12/30

神田優花、明日発売の新作「Cobra」(全2曲)、収録曲について。
1.Cobra
ダンスナンバーみたいな曲。バッキングはほぼシンセとリズムマシンだけで作っているんだけど、ラップが入るブロックにPungi(Snake Charmer)を入れている。普通曲が仕上がるプロセスって、バッキングが完成した後に歌詞が乗るんだけど、今回は歌詞に合わせて一部アレンジを追加した。珍しいケースではある。
Voは歌ありラップありVocoderによるコーラスあり、合いの手みたいな掛け声とかもあって盛り沢山。リバーブを全くかけてないんで、全体的にドライは仕上がり。
2.Love or Not
シンプルなオケにギターのミュートが絡む、みたいなイメージが最初にあって、そこに肉付けしたような曲。今聴くとコーラスとか、アレンジにはそれなりに手間暇かけているみたいなんだけど、その辺についての記憶が薄い。 まあカップリングなんで、たまにはこういうちょっと肩の力を抜いた曲があっても良いと思う。
- 12/24

橘高茉奈のニューシングル「Okay」、本日発売です。 以下、アーティスト本人からのコメント。
okay
ギターの音色がとてもかっこい良く、個人的にかなり好きな楽曲です
明るくてポップな曲調の中にかっこ良さがいい感じに出ている。
そんな素敵な形に仕上がりましたのでいっぱい聞いて欲しいです
Elephant in my room
この楽曲の意味を調べたら「誰もが気づいているのに、あえて口に出さない大きな問題」
って事なんですね
どんな思いでこの歌詞になったのか想像するのが楽しい様な、中々面白い仕上がりになった様な気がします
是非楽しんで聞いて下さい
橘高茉奈
- 12/23
橘高茉奈、明日発売の新作「Okay」(全2曲)、収録曲について。
1.Okay
割と純粋なPOPS。今回リリースする一連の作品群の中で一番気に入っている曲。
AメロとBメロのメロディーラインが音高も含め基本的に同じなんだけど、調・コード進行を変えることによってブロックの性格を色分けしている。 結構高度なことをやっていると思うのだが、言わなきゃほとんどの人が気付かないだろうと思って、あえて口にした。
音に関しては、チープ目なシンセブラスを中心にしたシンプルなPOPS。
2.Elephant In My Room
いわゆるチャールストンのような曲。作り始めた段階で、そもそも歌物にする気分が希薄だったので、イントロだけで1分以上あったりする。楽器編成は管が中心。あとフィドルとかパーカッション類。パート数は割りと多いかも。 箸休めみたいな曲だけど、たまにはこういうのもあって良いと思う。
SAM Coupeってイギリス製のコンピューターがある。おそらく皆さん知らないだろうけど、私も知らなかった。 何せ(廉価版モデル SAM Eliteを合わせても)12000台程度しか売れなかったと言われている(一説には数千台ともある)、商業的には完全な失敗作である。
それだけ普及台数が少なかったモデルであるのだが、驚くべきことにエミュレーターが(それも数種類)存在する。エミュレーター使用者の方が当時の実機オーナーより多いかもしれない。 スタンダードと言えるSIM Coupeとやらを私も入れてみたのだが、実に導入も容易で(インストールさえ必要ない)、洗練されたものである。 念のためAIに訊いたところ、合法でもあるらしい。
SAM Coupeの音源チップはPhilips SAA1099という。 6Ch仕様の矩形波(&ノイズ)発生装置。音自体にさしたる特異性はない上、愛用トラッカーにその音源の再現モード(多分かなりの再現精度のもの)があるので、エミュレーターを使っての音作りに食指は動かない。 E-Tracker2という(おそらく有志の手による)アプリケーションがあって、MODのようなサンプル貼り合わせ型の制作フローのようなのだが、プリセットのサンプルの質如何では使ってみるかもしれない。

- 12/19
MSM5232(無論非実機)を使った曲を書いている。 80年代前半のハイブリッド音源チップ。一応最大同時発音数は8。4Chずつの2系統となっている。 発音数8というのは、当時としてはかなりリッチな仕様だ。
しかしその8音、完全に独立制御はできない。 私も実はイマイチよく分かっていないのだが、CapacitorとExternalの二つのモードがあって、前者はエンベロープを一括で制御するらしく、4Chのエンベロープがほぼ同一の挙動を見せる。 後者の方がやや自由度は高いように思えるが、やはりトラック同士が干渉するというか、あるトラックの設定が他のトラックに影響する。
もう少し使い込めば色々分かってきそうな気がする。まあ今の時点でもマニュアルとか音源の仕様書の類を熟読すれば分かることもあるのだろうけど、面倒臭くて手を出していない。 今作っているChiptune物は、来年以降の神田優花の作品として公開されると思います。
- 12/18
筝(そう)について考えていた。 いわゆる(日本で言う)琴のことなわけで、「以下便宜的に琴と言う」みたいに稿を進めて行きたいところなのだが、琴というのは明らかな誤用(琴(きん)というのはハッキリと別の楽器)である。 気持ち悪いので筝のまま進めさせてもらう。
基本13弦の楽器で、各種の調弦があるが絶対音高の指定はない。 調弦法≒スケールなわけだが、スケール外の音を使うことはあっても、特殊奏法に近い。 一応、曲中にチューニングそのものを弄る「柱(じ)移し」や、押し手による一時的な音程変化(チョーキングのようなもの)がある。しかし柱移しなんて、奏法というより儀式のような色合いすらある。
固定スケールというのは、即ち制約なわけだが、物事というのは制約が成立させている。これは森羅万象に例外はない。 筝の調弦など、西洋楽器に比べれば不合理極まりないが、それによって生まれた何事かも当然あるだろう。
スーパーカセットビジョンの音源部であるuPD1771、最大同時発音数は1である。厳密には複数音の同時発音が可能なのだが、旋律線は一本に限られる。 楽曲を作るには実に重い制約で、実際に曲(ゲームBGM)を聴いても、当時の音屋の苦労が偲ばれる。 ただし、その制約から生まれたような独自の書法も見て取れる。
今作っている曲に、筝のスケールを取り入れようと思っている。 筝曲や筝そのものの音を使うわけではなく、あくまで音の配列のみ拝借したい。音についてはChiptuneである。
- 12/17

神田優花のニューシングル「Fairy」、本日発売です。 以下、アーティスト本人からのコメント。
Fairy/Cabaret
Fairy
歌いたかったのは、未来への強気な期待感の中ににじませた、ほんの少しの不安。だからこそ、夢をみるんだという正直な気持ちです。
そこは切り離しては考えられないなと思ったから。
期待も不安も、ままならない気持ちさえ楽しめたら、もしかしたらそれって最強かもしれないですね。
強さだけで引っ張らないように、ファルセットの使い方は考えました。
Cabaret
歌詞中に何度も出てくる、まさに『好きなように』が全てで、明確に人物像を思い描きながら歌ってたから、歌的にはそんな苦労した覚えはないんだけど、とにかくレコーディング後が大変だった曲。
今季出す曲たちの中で、いわゆるドレミ音階ではない音源を使った曲がいくつかあるんだけれど、(詳しくは割愛するけども)この曲はその中でも特に、今までと違ったアプローチを必要とした。というのも、当初の予定ではオケに使われている音の方に寄せて、ドレミ音階とは一部離れた音で歌うってことにしてたんだけど、マスタリング段階で、この曲は一番そのあたりの違和感が強く出てしまって。
数々の変遷を経て、最終的に今の形に収まったんだけど、録り終わってからのチェックがとにかくくせものだった曲でした。
あーでもない、こーでもないって一番やった曲だったかも。
仕上がってよかった。
よかったら聴いてみてください。
神田優花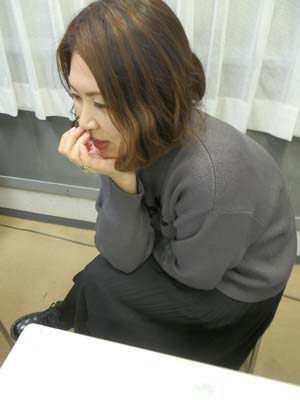
- 12/16


今年は仕事納めが例年より早い予定で、年内にやるべきことを急いで終わらせている。 だからかどうか、事務仕事上のミスが多くなっている。疲れてるのかも。
神田優花、明日発売の新作「Fairy」(全2曲)、収録曲について。
1.Fairy
80年代くらいのJ-POPのイメージ。バブリーな。
バンド編成にシンセ(主にFM)を加えたようなシンプルなアレンジ。コーラスのパートとかはやや多めなんだろうか。バッキングのパートの中ではギターに時間かけた覚えがある。
ラストはフェイドアウトなんだけど、そういうところも当時のPOPSっぽい。
2.Cabaret
これもフェアライトのエミュレーターで作った。リズムが跳ねている、いわゆるシャッフルなんだけど、フェアライトのシーケンサーはちょっと特殊で、入力にコツが要った。アレンジはブラス中心。基本的にPOPSなんだけど、この曲もエミュレーターの作りの甘さに悩まされた。特にVoの処理。
フェアライトって、サンプルを貼り合わせて曲を作るような(もっと多彩な機能があるが、私にとっては)、MOD作成などと似た構造なんだけど、MOD系のツールの方が遥かに安定している。もう今後、なるべくそのフェアライトにエミュレーターは使わないようにしたい。特に商品制作用途には。
- 12/11



自民党とは、利権のジョイントベンチャーのような集団である。利権(≒金)を原動力としている以上、利をもって篭絡するのに実に容易い集団である。現在の、隣国の工作員のような政治家らを見るにつけ、詠嘆してしまう。
日本人には原理がないと言われるが、そんなことはない。Bookishな、整理・体系化された原理がないだけなのだが、だからこそ厄介な面もある。文化大革命が起こしにくい。
古を尊ぶ「述べて作らず」といった精神が、アジア(儒教圏)の大停滞をもたらした面は大きかろうが、今の日本の老人至上主義を見ると、今後清朝末期のようなカオスが待っているかもしれないと思えてならない。少なくとも、我々日本人は今後、今より遥かに貧しくなるだろう。 そういえば本田宗一郎が「日本の戦後復興・経済発展は、ジジイがいなかったから達成できた」みたいなことを言っていた気がする。
今の日本は、政府でも民間でも、年長者が基本的にイニシアチブを握る仕組みになっている。判断は旧態依然とし、改革や新たな発想を拒む。制度は常に年長者・先占者に有利となり、そんな人らに百年の寿命を与えたら社会はどうなるか、その壮大な実験のような国になってしまっている。
- 12/10

橘高茉奈のニューシングル「Maybe Maybe」、本日発売です。 以下、アーティスト本人からのコメント。
maybe maybe
今回の曲は途中の感想部分にスキャットを少し入れさせて頂きました!初挑戦で大変でしたが楽しく出来たので最後まで是非聞いて下さい
Girl Like Me
何時もより爽やかな楽曲です
この曲を聞いていると大空の下にいるような、爽やかで暖かい曲感覚になります
癒しになるような曲なので是非聞いて下さい
橘高茉奈
- 12/9

橘高茉奈、明日発売の新作「Maybe Maybe」(全2曲)、収録曲について。
1.Maybe Maybe
ファンクっぽいPOPS。女性Vo2~3人のユニゾンとかでも良かったかも。
なんかこれ、レコーディングでコーラスを一部録り忘れてて、再度歌入れをやった記憶がある。だからVoトラックは複数日にまたがってレコーディングされてる。
間奏部分にフェイクみたいなのがある。こういうのについて、普段私はあんまり注文を入れないんだけど、この曲に関しては作曲時点での構想だったので、軽く注文入れさせてもらった。完全なアドリブではないけど、キッチリ事前に詰めたものでもなかった。暫くレコーダー回しっぱなしにして録ったテイクを編集段階で切り貼りした。
2.Girl Like Me
物凄く昔に作った曲で、細部については本当に記憶が薄い。FMシンセを多用したPOPS。
いわゆるストックを引っ張り出してきたケースで、歌い手の音域に合わせて作っていないので、ベストなKeyではないかもしれない。バッキングトラックがほとんど完全に出来ていたので、移調までしなかった。
- 12/8



また更新間隔が開いてしまった。今このHPをリニューアルしようと思ってて、試作品を作っていた。全面的なリニューアルなんだけどデザイン考えてる余裕がなくて、とりあえず今のデザインを踏襲したものを作っている。 今のは今年一杯で終了の予定です。URLとかは変わらない。
- 12/3

神田優花のニューシングル「Extravaganza」、本日発売です。 以下、アーティスト本人からのコメント。
Extravaganza/Queen Of The Night
Extravaganza
エクストラヴァガンザさんです。
リハには時間をかけました。ゴキゲンな曲なので、お調子者のノリで歌ってます。メロディなんてあってないようなものです。声色とか発声の仕方とか実験に実験を重ねて作りましたが、まぁ私的に酔っぱらいの歌と思ってます。怖いものはないわ的な。
ちなみに、冒頭や間奏で出てくるコーラスも私です。イメージしたのは幽霊のような声。調子っ外れはわざとです。
つまりは悪ふざけです。
Queen Of The Night
この曲は70年代の突っ込んだ歌い方がテーマの1つ。とっかかりはなかなか掴めなくて悩みましたが、自分で自分に合いの手を入れるような、1人コーラスグループ、みたいなものをイメージしてからは、今の形に固まりました。
レコーディングでは5人くらいで臨んでる気分でした。
全部自分ですけど。
こんなん出来ました、という気分です。
どうぞ。
神田優花
- 12/2

神田優花、明日発売の新作「Extravaganza」(全2曲)、収録曲について。
1.Extravaganza
ちょっとおどけたようなロックナンバー。これもフェアライトのエミュレーターで作った。アレンジはシンプルなバンド編成にオルガン加えたもの。
イントロのコーラス、そもそもビブラート(唱法)で歌ってたんだけど、欲しいニュアンスに届いてなかったんで、編集段階でビブラートエフェクトをかけた。あと全体的にVoのフォルマント弄ってる。
バッキングの核はベースなんだけど、Jazzとかのウォーキングラインみたいな。スケールは(メロディックマイナーとか)クラシック的なんだけど。
2.Queen Of The Night
これもフェアライトのエミュレーター。バンドアレンジにアクセントとしてブラスを加えたような。1分台と短い。因みにタイトル曲も2分くらい。
70年代とかのサイケデリックロックみたいなものをちょっとだけイメージしたんだけど、当時の女性コーラスのニュアンスが中々再現できなくて困った。今もそこについては納得していないんだけど。
Vocaroidとかの商品ラインナップがもっと充実していて、こういうマニアックな用途にも対応していてくれたら助かるのにな。AIとかで代替できるのだろうか。
- 11/28
MSM5232について。沖電気製のアナログ(厳密にはハイブリッド)音源チップ。 一部のアーケードゲームやキーボード類に使われた。 沖電気から発売されていた製品であるのは確実なのだが、KORGとの共同開発だったとか言う話も散見され、エンジンが(主にKORG社製の)キーボードに搭載されていた形跡がある。
全8Ch、矩形波(方形波)に周波数偶数倍の音を付加して音色を作るという、オルガンのような仕組みである(ノイズも使える)。偶数倍というのは要はオクターブ上の音なのだが、音源方式として珍しいと言えば珍しい。 因みに、倍音減算式シンセサイザーなどによくある「倍音構成」を弄って波形スペクトラム自体をカスタマイズするタイプではない。 偶数倍音を付加するのでなく、周波数偶数倍の音を加えて和音にする。 8Chと言うのも、発売された80年代初頭としては豊富な同時発音数で、音屋にはそれなりに重宝されたろう。
驚くべきことに、私が愛用しているトラッカーにそのMSM5232音源モードが搭載されている。 実機など無論扱ったことがないが、文献を見るだに、かなり忠実な再現が為されているらしい。 それを使った曲を作りたいところなのだが、今のところそれを活かせる曲想がない。 とりあえず音色でも作ろう。
- 11/27
中国さんが随分とお怒りのようで。 威嚇・恫喝的な行動を繰り返しているようだが、基本的に怒りというのは恐怖である。 彼らは「僕は今こんなに怯えています」と表明しているに等しい。 中国共産党トップにとって「台湾有事」は、我々一般日本人に比べ遥かに濃厚な現実なのだろう。
六韜や孫子などを読めば自明だが、中国人というのは認知戦をお家芸とする(と言うことになっている)。 現代日本にも、膨大なコストをかけて認知戦を仕掛けているのだが、しかし現状を見るだにあまり効を奏していないようだ。 間諜のような人たちは、もう少し「親中」的な世論を醸成することはできなかったろうか。
日本国首相の発言については、間違ったことを言ったわけではないのだろうが、政治的には失言なのかもしれない。 しかし相手が激高しているからと撤回などしては、それこそ相手の思う壺。「日本人には恫喝が効く」と思わせてしまう。 ここは半ば無視しつつ、粛々と必要な措置を進めれば良いと思う。 あまり挑発の応酬になるのも大人気ないので、そこは政治家諸氏にそれこそ政治的手練手管を発揮してもらいたい。
現中国が台湾を併合したいというのは本当なのだろうけど、アメリカなどを相手とした「対外戦」は望んでいないはず。 何故なら、漢族というのは伝統的に戦に弱い。弱いが故にそれを忌避する感覚が強いと思われる。 アメリカ人が戦争好きなのも、ほとんど負けたことが無いからだ。
歴代中華帝国で対外戦に強かったのと言えるのは、唐・元・清など、どれも異民族王朝ばかり。宋・明と言った漢族王朝って伝統的に弱い印象。兵員の資質に決定的な問題があるのだろう。 漢人の言う勝利って、抗日戦争とか欧米からの侵略を跳ね返したとか、そういう抵抗・暴発のようなものや、あるいはほとんど丸腰の相手に一方的に攻め込んだとか、そういうのばっかり。 今後本当にアメリカと戦争になったりすれば、局地的敗戦を機に全体が瓦解するような事態になりそう。泗川の戦いとか、知らない人は調べてみたら良い。彼らの本質が窺い知れる。 失礼ながら私の中国人に対するイメージ。 今の中国があんなにナショナリズムを煽るのも、近代的国家感の形成に失敗しているからだろう。
中華世界における士は(前近代の日本と違って)軍人を指さなかった。 むしろ伝統的に兵を蔑む感覚すらあったはずで、日本史で言うなら古代(平安期)の武士あたりに近い扱いだったろう。日本の武士道のような思想・倫理も生まれなかった。 無論現代においても、その価値観をドラスティックに上書きする思想は生まれていないはずで、基本的に兵の素質もさほど変わっていないだろう。 その上国家と自身とを同一視するような国民国家的な感覚も育っていないのだから、戦闘能力も疑わしい。
あそこまで異民族や周辺国との領土問題を抱え込んでしまっている以上、一敗は戦慄に値しよう。 台湾の併合に失敗したら、チベットもウイグルも、内蒙古だって東三省だって、その他多くの少数民族だって独立を言い出しかねない。 実のところ経済もボロボロなのだから、一気に清朝末期のような様相を呈してこないとも限らない。
中国の主張・言動を冷静に分析してみると良い。 台湾と言う女を無理矢理にでも我が物にしたいが、喧嘩は怖く、とにかく外野に関わってきて欲しくない。徹底的に二者関係に持ち込みたい。 日本の呟いた「関わるかも」の一言にあの取り乱しよう。 気分が伝わってくるじゃないか。 ただ、臆病者には「何するか分からない」という怖さはある。
北朝鮮はあれほどの軍国主義国家で事実上の核保有国でもあるのだが、私は北朝鮮が開戦するとしたら、国家元首の精神不安によるもの、ぐらいしか考えられない。戦争と言うより暴発。 何故なら朝鮮人も戦争の経験が無いから。
朝鮮人の言う戦争って、日本を含む外国勢力の侵攻に抗ったとか、朝鮮戦争のような(時に援軍を巻き込むような)内乱しか指さない。 近代における厳密な意味での戦争って大変で、どんな国にでも遂行できるようなものではない。 独立した近代的ステートで、近代的軍隊・装備を持ち、最低限の兵站が可能で、外交パイプを持ち、宣戦布告などを行え、ある程度国際法などに則った継戦ができねばならない。 今の北朝鮮にできることって、38度線を破るような暴発とか、突如他国にミサイル飛ばすとか、その程度だろう(やった途端に国家は消滅する)。年単位の(アメリカなどとの)戦争なんてまず無理。
民族って固有の型から抜け出すのは難しい。 日本も、大東亜戦争のような狂気を発動できる民族だからこそ、いつまでもコロナ騒動みたいなバカ騒ぎを起こし続ける。
- 11/26

神田優花のニューシングル「Afterglow」、本日発売です。 以下、アーティスト本人からのコメント。
Afterglow/Grasshopper
Afterglow
音の運びとしてはそう難しくはないんだけど、キラキラとした言葉のつぶが伝わるように、いつも以上に発声終わりの繊細さと丁寧さを心掛けた曲です。
その気分、伝わるといいな。
Grasshopperは、ひとりごとをひっそりと歌うような、そんなゆるりとした世界観で歌いたかったんだけど、如何せん全体的に高音域なもんで、どう料理しようか頭を悩ませた曲。結果、端々に小手先も駆使したわけだけど、それがあんまりわからないといいなと。じゃあ、ここで言うなよって話だけども。
なかなか、ゆるく多幸感ただよう曲になったんじゃないかな。
ゆるりと、聞いてみてください。
神田優花
- 11/25


神田優花の新曲「Swells」が「FORMULA URBAN」でオンエアされました。 ヨーロッパ圏のラジオプログラムです。
神田優花、明日発売の新作「Afterglow」(全2曲)、収録曲について。
1.Afterglow
POPSですね。POPSナンバーだけでアルバムを作ろうと思っていたんだけど、予定通り作るなら多分それに収録される。
バッキングのギターを12弦にするかナッシュビルにするか迷ったんだけど、結局後者にした。間奏のサックス、最後のあたりにハーモニーを入れてるんだけど、ハーモニーのパートを加えたわけでなく、ハーモナイザーをかけている。その程度のことなんだけど、あんましやらないアプローチではある。
コードから作ってて、比較的そこに拘ったろうか。後付の感はあるけど、歌のメロディーは好きですね。
2.Grasshopper
レゲエライクなPOPS。途中のコーラスワークなんかはゴスペルっぽい。
構成がちょっと変わってるんだけど、何と言うか気分の赴くままに作っていたらこうなった。普通ならもっとシンプルにまとめるところなんだけど、あえてそのままにした。
アレンジはアコギ中心。アコギ一本で作って他のパートを肉付けして行ったような。
- 11/19

神田優花のニューシングル「Swells」、本日発売です。 以下、アーティスト本人からのコメント。
Swells/Romantics
Swells
多くの展開、多くのパートで成り立ってる曲。その全てが際立って細部まで気の抜けない楽曲でした。
パートの1つ1つがどう重なって、どう響いていくのかを考えながら歌を組み立てるのは楽しかった。
必ず誰かに届く、そんな確信のような、祈りのような気持ちで歌いました。
Romantics
あまり力を入れないように、クセは持たせて、でも濃さはあってもサラッと、というよくわからないメモを楽譜に書いてました。どこかのラーメンのダシのようですね。
曲的には、歌ってるとどこかへ引きずり込まれそうな中毒性とか、ちょっと軽薄な感じがするくらいにコーラスでは遊んだりとか、楽しんでやりきりました。
今年の配信第一弾になります。
楽しんでいただけますように。
神田優花

- 11/18

神田優花、明日発売の新作「Swells」(全2曲)、収録曲について。
1.Swells
EDMというか、シンセサウンド。生楽器の類を一切入れてない。 延々と同じベースラインがで進行して行くような、構成自体はシンプルな曲。
音に関しては、聴いた感じゴチャゴチャしているようだけど、ほとんどシンセ(とリズム)のみで、パート数は少ない。 Voもエフェクティブだけどハーモニーとかほぼ無くて、こちらもシンプル。
2.Romantics
ニューロマンチックみたいな曲を作ろうと思った。タイトルもそのままなんだけど、私が付けたわけではない。 一時期フェアライトのエミュレーターにハマってて、その時に作った十数曲のうちの一つ。
そのエミュレーター、サンプルの類のピッチ制御が甘くてレコーディング作業が難航した。当初Voのピッチ補正を施さないつもりだったのだけど、曲折あって結局楽音ベースでやることにした。 ある種の音のチープさがツボだったんだけど、完成したものを聴くとさほど他のトラックとの違いは感じられないような。
ついでながら、この稿でエミュレーターという用語を使っているが、厳密な意味でのエミュレーションを行っているツールではない。単にフェアライトの挙動やインターフェイスを模したアプリケーションというところなのだが、適当な短い名称を知らない。
- 11/16
「商は詐なり」と、老中松平定信は言ったのだが、江戸幕府が殊更にそれを是としたのではなく、広く儒教圏にはそういう物の見方が根付いていたし、それがアジアの停滞、近代化阻害の一因となっていた。 人類史における近代資本主義は、この「商」をどのように思想的に位置付けるかが、一つの重要な課題となっていた。 現代には、商を含む経済を割りかし肯定的に捉える風があるのだが、そもそも日本社会は、儒教的呪縛が薄くて、それが近代化を容易たらしめた大きな理由だったと思われる。
それでは現代社会は、商を蔑む感覚を完全に払拭できたのかと言うと、そこは疑わしい。例えば転売を悪とする風潮などは、根底に商をそこはかとなく薄汚いものとする感覚があるものと思われる。 これは単なる儒教・儒学の影響なのか。ユダヤ人が差別された理由にも商業蔑視があるのではないか。 人間には、その本然として商を蔑む感覚が備わっているような気がする。 特に日本人のようなメタフィジカルな思考が苦手な民族は、その感覚を克服するのも困難と見えて、それが今の停滞の遠因となっているように見える。
商の才とは、利を得るため、相手に合わせて自らの態様を変える能力である。だから時にペテンのようなものと紙一重となる。 額に汗して働くより、その上前を撥ねる方が効率的であるからこそ金融・投資・情報と言った分野は発達した面があろう。 このように総括すると、どうもそれが碌でもないものに思えてくるが、前近代の人にとって、これは常識的感覚でもあったはずだ。 私においても、詐なりとまで言わないまでも、それに深く手を染めることはこれからも無いものと思われる。 その能力も無いし、そこに憧れもない。 少なくとも、純粋な芸術に、商の匂いは嗅ぎ取れない。
しかし、人間の商に対する動機は、我々の日々の生活の足しになっている。人類にとって(少なくともこの段階において)不必要なものではないのだろう。 この先の未来、どうなっていくのかは分からないけど。



- 11/12

広瀬沙希のニューシングル「kaii」、本日発売です。 以下、アーティスト本人からのコメント。
kaiiは多数派から見た少数派の人間を、理解出来ない不可思議な存在として描きました。でも逆も然り、少数派から見た多数派もまた理解出来ない不可思議な存在なんです。大事なのは理解出来ないもの、自分とは違うものを排除するのではなく、お互いのいいところを認めてダメなところは補い合っていくことですよね。
そんな単純なこともこの社会は出来てないんだなと感じる今日この頃です。
「inner child」という言葉は心理学の概念として存在します。意味合い的にはそのままに、私なりの視点で表現しました。少しでも共感してしまう人に送ります。
広瀬沙希
- 11/11
公明党は自民党との連立を解消した。 表向き(公式)の理由は、裏金問題への対応を不服として。
両党のトップ会談にて、自民党側は「その件の対応については即答しかねるので一旦持ち帰る、と伝えたところ、突如その場で連立のご破算を言い渡された」と言う一方、公明党側は「以前から重々申し伝えてきたことだ」と言い、両者の主張は食い違っているとされる。 自民党新総裁の就任直後の連立解消など、(その保守思想に対する)明白な当てこすりである、と言う感想が見られたし、公明党の党首が、破談の直前に中国の大使と会っていたことなども問題視されている。自民党が他党に秋波を送っていたのが(公明に対して)非礼である、と言うような意見も見られた。 果たして正しいのはどちらか。
人間やその集団の意思決定のプロセスは複雑である。何かが物別れに終わる際、その理由を端的に言うと「その関係が維持されるだけの十分な条件が揃わなかったから」である。 人はすぐその契機について詮索したがるのだけど、それは大抵口実に過ぎず、破談はそれ以前に決まっているものだ。切り出すのに理由が要るだけ。 ハルノートが無かったら日米は開戦に至らなかったのか。違うだろう。あの当時、日米の開戦はおそらく不可避だった。
男女の関係など分かりやすい。 例えば別れを切り出す女性が、原因として相手の何らかの行動を指摘した際、男の側が「それでは俺はそこをあらためる」と弁明したところで意味がないのは感覚的に分かろう。破綻の理由とされた何かだけをRepairしても仕方ない。 物事の終焉は、当事者のどちらかが悪いから起こるわけではない。
物事が続くには、続くだけの理由が要る。 関係と言うのは、ある事件がそれを絶つのではなく、続いて行くだけの条件・理由が無いから絶える。厳密に言うと、その関係とやらが、実は存在していなかったことに当事者が気付くのに時間が必要だっただけ。事件と言うのは口実となるだけ。それはそれで物事が進むのに必要ではある。
何故そうなのか。我々人間が有限の存在であるからだ。理由なしに物事が続いて行くような非競合的世界に生きていない。だから何かが続くことには、必ずその理由がある。続くものには、続くだけの価値がある。 どうしてこれが常識とならないのか、私には不思議でならない。何故大人は子供にこれを教えないのか。これは大人の側がわかっていないからだろう。
自公の連立は四半世紀以上に渡って続いたらしい。これは比較の上でかなりの長期であるそうな。日米同盟は70年以上続いており、国家間の同盟関係としては異数のものであると言う。我々は二千年続く共同体に生きている。
二千年続くものがあり、百年続く何かがあり、一年しか続かないものがあり、一日で消えるものもあり、数時間・数分・数秒で消えて行く何ががあり、条件の欠如により、そもそも生まれてすら来られなかった何かがある。 でもそれらは皆、大別(二分)するなら同じもの。 私が今日も追いかけ続けているのは、それらとは全く別の何か。永遠なるもの。
- 11/5
神田優花のWendyが「Formula Emergenti」でオンエアされました。 ヨーロッパ圏のラジオプログラムです。 多分来週、新曲のSwellsが同プログラムでオンエアされます。
スーパーカセットビジョン(SCV)の音源部を使った音楽を作る方法は今のところ存在しない。独自のサウンドフォーマットも存在しない。 サウンドフォーマットはさておき、SCVのサウンドを再現するためのツールはいずれ登場するだろうと思われるが。
一応SCV音源の再現を謳ったプラグインシンセが存在するが、試用版を使ってみたところ、完全再現には程遠い。 SCV音源は「矩形波三和音・ノイズ一音」の合成音が一種の「売り」なのだが、そこが再現されていない。 再現されているのはモノフォニックモード(単音)のみで、なんとも中途半端な代物だ。
矩形波三音とノイズの合成音程度のものなら、完璧に同じものはさておき、似たようなものなら簡単に作れるわけだけど、私はあくまでSCV音源を再現したいと思っているので、それでは事足りない。 とあるトラッカーにSCV音源機能が実装されそうな気配があるので、それを待ちたいと思っている。
合成音が出せはするのだが、あくまでSCV音源は単旋律しか表現できない仕様である。音楽作品を作るのにこれは大きな制約だが、実際のプレイ動画をYoutubeなどで確認すると、効果音によってBGMが寸断されているものもあれば、二つの音が同時に鳴っているケースもそれはそれである。 ポリフォニーを表現できるわけでなく、おそらくはプログラミングの工夫(二音の高速切替等)によって、擬似的にそれを表現しているだけだと思われる。 サウンドチップの制御において、前例のない手法ではない。
しかしその高速切替などを、トラッカーで再現可能になるだろうか。 トラッカー作者の根気にもよるだろうが、きっとそこまでの機能は実装されないような気がする。
今、SCV音源を前提とした曲作りに入っているのだが、今後のツールの登場を見込んで作っているような状態で、どの程度のことが実現できるか不透明である。 まあそれでも可能な限りのところまで追い込むけど。
- 11/4
熊害事件が、史上例を見ないほどに多発しているそうだ。連日被害の報道が相次いでいる。 現場では一種のパニックが起こっているものと思われる。新型コロナウイルスにあれだけ戦慄した民族である。まあそうなるだろう。
コロナ騒動は流言に端を発した集団発狂で、取り立てて対策も必要なかったタダの風邪だが、熊はそうではない。 数字上も明らかに被害件数が増えているし、多分熊の個体数も増えているのだろう。凶暴化もしているのかもしれない。
自衛隊を出動させるとかさせないとか、そういう話にも発展しているようなのだが、やはり銃器の使用などについて、法的な問題があるようだ。 この件にかこつけて、一気に憲法改正してはどうか。 内閣の支持率も今高いようだし、熊対策に必要だと言えば国民投票でも改憲派が多数となるのでは。 恐怖に付け込まれれば正体を失うような民族だし、ここは一つ熊さんにがんばってもらいたい。




- 10/31
現首相がアメリカ大統領と会談を行ったらしいのだが、その時の態度が一部に不評を買っているらしい。曰く「媚ている」だとか。
私には好悪どちらの感情もまるで沸いてこない話なのだが、人は所与の条件を行使する権利を持っているとは思う。彼女には、女であることを武器に生きて行く権利がある。 国益に適うのなら許容して良いのでは。
私が女性の態度に感想を持つとすれば、それは主に主体性の有無において。 主体性のない媚態は気持ち悪いが、それはあくまで主体性の無さの部分がであって、マドンナがコールガールやってたとしても全く問題ない。


- 10/27
あるジャーナリストというかテレビタレントの、テレビ番組内での現首相に対する発言が大変な問題となったらしい。 本人は謝罪し、番組は終了(25年続く長寿番組だったそうな)、番組スタッフも処分されたという。 いまだ波紋が収まっていない。
テレビタレントというのは、「100メートルを10秒で走れ」という命令を正確に実行できる者たちである(と私は理解している)。 10メートルに20秒かかるような鈍足では話にならないが、9秒で走り抜ける者もお呼びでない。まあ繊細な作業である。
地上波のテレビ番組の司会者などを眺めていて、「この人は一生この世界で食っていけるだろうな」といった感想を持つことがある。 100メートルを10秒ジャストで走れるような人である。 上のタレントさん、テレビという世界で生きていくのは難しいのかもしれない。 それは必ずしもジャーナリストとしての能力に欠けることを意味しないが。

- 10/22
北海道で鳥インフルエンザが確認されたとかで、46万羽近い鶏が殺処分されたと言う報道を目にした。 また卵が高騰したりするのだろうか。
私に疫学的な知識は無いが、全羽の殺処分まで必要なのだろうか。またコロナ騒動と同じく過剰対策でないかと疑ってしまう。 大体ウイルス感染が発覚する度に全羽皆殺しにしていたのでは、免疫・耐性を持った個体がいつまで経っても生まれないではないか。
11/19(水)、神田優花のニューシングル「Swells」が発売されます。 この先、年内にもう4タイトル発表する予定です。是非チェックしてみてください。
- 10/14
鮫とイルカは外見だけ見ると瓜二つである。 ある面に照らせば、生存上、あの形態が合理的なのだろう。 中生代にいた魚竜も見た目はイルカにソックリだ。 収斂進化の典型例で、イルカは我々人類と同じ哺乳類。鮫・魚竜はそれぞれ、魚類・爬虫類に属している。外見が似ていても知能などは隔絶している。
ある目的を同じくした場合、別の目的を異にしていたとしても、形状だけは瓜二つとなることがある。 魚竜とイルカも、同時代に存在したなら、魚竜の方が生態系上の上位のニッチを占めた時間があるかもしれない。
病に苦しむ人を救うため、「愛」を核に医の道に臨む者がいる一方、「医者は金になる」とか「医学の世界でノーベル賞級の発明をしてその権威に与りたい」と思う者がいたとして、両者の日々の研鑽作業自体は、周囲から見分けが付かぬほどに似ていたりしよう。 片やは時にSTAP細胞を発見してしまったりして、馬脚を現したりするわけだが。
諸々の問題を抱える日本人だが、ある時期、あれだけの経済発展を見せたではないか、と思われる向きもあろうと思うが、私はそれを魚竜の栄華でないかと疑っている。 別の原理を持って動いている集団が、表面上類似の態様を見せ、ある時期・ある側面において優位性を持つことは、現象としてあり得なくないからだ。 個人的には杞憂であって欲しいのだけど。 因みに魚竜は滅び、こんにちその姿を見せることはなくなった。
- 10/13
この度の自公の分裂、私は政治や選挙には詳しくないのだが、公明党の要求は到底自民党の呑めるような内容でなかったと言う。 公明党は連立解消ありきで交渉に臨んだのだろうか。
解消ありきであったかまでは分からないが、両者は袂を分かつべくして分かったとは言える。 一個人や集団の意思決定のプロセスは複雑である。 幾重にも要因が重なり合い、ある結論に至る。関係が決裂するのは、決裂しないだけの最低限の条件を欠くからで、今回の一件もその最低限の条件が維持できなかったのだろう。
自民党のような利権集団・集金機構にとって、件の要求は到底呑めないものであった。これは事実なのだろう。 私はいわゆる「裏金議員」などにさしたる問題を感じていない。一個人の背信・背徳行為、それはそれで糾弾されるべきなのだろうが、問題の本質はそこではなく、自民党と言うスキームそのものにある。 だからその条件を到底飲めない自民党には、政治の世界から退場願うしかない。 諸悪の根源であるからだ。
新しい総裁に期待する声があるようだが、私は良くも悪くも大して何も変わらないと思っている。 何故ならその人とて自民党というスキームから生まれ、這い上がってきたからだ。周りを固める人材も、末端に至るまでそのスキームが生み出した物であるから。 表面を飾る何かでなく、核にある思想について言及している。
失われた30年とかよく言われる。 いわゆるイノベーションも、世界的成功を収めるベンチャー企業も興らず、既存の産業は一部例外を除き壊滅状態。 時折起こる政府主導の産業育成政策は悉く失敗。既得権保護を事とし、(新技術などでなく)単なるアイディアであるライドシェアさえも政治によって潰される、先進国でも類を見ない腐敗した体制。 タクシー業界は票を持つが、ライドシェア業界は現時点で存在しないから票を持たない。だからして生まれる前に芽を摘まれる。
積みあがった赤字国債の発行額も、要は既得権保護の結果である。今の有権者は票を持つが、後世・将来の日本人は票を持たないから、そいつら名義のツケならいくら膨れ上がらせても構わない。 少子化の原因は単純ではないが、この体制に少子化が起こらぬはずがない。
政治の腐敗も有権者の堕落も、要は自己保身・自分の利益しか考えない者の末路である。そういう人らが形成する社会が、こんにちのように荒廃するべくして荒廃した。
人間という生き物が、生きることそのものを目的とせず、あまつさえ手段とすることなど可能なのであろうか。 可能であるに決まっている。そうでなければこんにち、人類は猿など他の哺乳動物と未分化であったろう。 生きることそのものを超えた至上の命令、それが意志であり理性であり夢である。 人類の一員と見做されながらそれを持たない日本人は、ネアンデルタール人などが滅びたように、つまりは淘汰の過程にある人モドキなのかもしれない。


広瀬沙希のニューシングル「kaii」の発売が11/12に決まりました。 詳細はまたあらためてお知らせします。
- 10/11
プロテスタンティズムや近代的資本主義が、人類の進歩を促したように、人間は自律的にモノを考えることによって成長してきた。 痛みこそが、人々にモノを考える切っ掛けを与える。
政府が金をバラ撒けば、それは税という形で国家構成員に跳ね返ってくる。だから健全な市民であれば、政治によるそういった行動を牽制する圧をかけて当然なのだが、今の日本にその圧は起こらない。何故なら現政府は、納税者にその痛みを感じさせぬよう、巧妙に赤字国債というモルヒネを打ち続けてきたから。結果政府の借金は1400兆円規模に膨れ上がったわけだが。 モルヒネは確かに効いていたが、その間にも病状は進行し続け、もはや取り返しがつかない状況に至っている。 つまり現日本人は、深刻な病魔に侵されている。 これから未曽有の痛みを味わうことになるかと思うが、これも進歩の奇貨とするしかない。
- 10/10
公明党が連立を離脱したらしい。 私は、あの党にもその母体である創価学会にも特段の好意は持っていないのだが、今回の件については「原則を貫いた」という点について、少々見直した。 大臣のポストももう要らないということなのだろうから。 さすが日蓮宗の本流とも縁を切っただけのことはある。 無論、自民党という「沈みゆく船」から逃げ出したという面はあろうが。
それにしても自民党は公明党を見くびったな。 言われている「政治と金の問題」。それ自体は彼らがやらかした(現在進行でやらかしている)悪事の中では実に些末なことと言えるが、それすら有耶無耶にするつもりだったのに、そうは問屋が卸さなかった。 公明党には「お前らも一味だろ?大臣のポスト(利権)にもありつているじゃないか」という気分で高をくくっていたのだろうが。 我々は今、滅びゆく者の醜態をまざまざと見せつけられている。
これから一層政治は混沌とするだろう。 自民党が単独で過半数を回復することなどは、少なくとも私が生きているうちには無さそうに思える。それどころか、自民党は崩壊するかもしれない。 あのような利権・金権集団には、「政権」という旨味があればこそ群がってくる何事かが絶えないわけで、それがなければ原理上、坂を転がるような衰勢をたどるに違いない。 無論あれほどの大所帯なのだから、綺麗サッパリ雲散霧消するなんてことはあり得ないが、老舗の泡沫政党(例えば共産党のような)として細々とやっていくことになるかもしれない。 あるいは大政奉還後の徳川宗家のように、一諸侯としての政治参加こそ許されぬものの、一定の権威として遇されるような存在になるか。
自民党の新総裁は、最後の将軍徳川慶喜になるかもしれない。 江戸末期、衰え行く徳川幕府にあって周囲の嘱望を集めた彼こそが、幕府に引導を渡すことになった。
政権を取って代われるような野党が見当たらないのが多少気になるが、それも大した問題ではないのかもしれない。 あれほど「攘夷」で時の政権に揺さぶりをかけていた幕末の志士らによって作られた明治新政府が、それまでの言を忘れたように開国路線を採った。 当時攘夷が不可能であったように、誰が政権の座に就こうが、今の日本の状況で減税と物価高対策を同時進行させるような奇術のようなことが可能であるはずはなく、どのみち緊縮かインフレによる債務踏み倒しに進むしかなくなる。 それにしても、その「来るべき日」の被害をこれ以上深刻化させないように、自民党という政党には、政治の世界から退場してもらうしかない。
- 10/7
AIの作曲機能はもう実用レベルに達しているようだ。普通に商業音楽と区別が付かない。 実は自動作曲のようなプログラムは数十年前から存在するのだけど、カスタマイズの自由度といい、現行のものは一つの完成形と言える。
地下アイドルとかの企画をやっている比較的小規模の事務所さんなんかにとって、音楽(オリジナル楽曲)はとりあえず必需品である。 だからそういうところから仕事を貰っている音屋は昔からいて、私の知り合いにもいる。 ところが最近、その手の仕事もなくなりつつあるようだ。 無論AIが代替しているから。
「音楽クリエイター(AIで作曲ができる人)募集」みたいな求人を見かけた。 AI使うなら事務所の社長やスタッフが適当に作れば良いのだけど、それすら面倒なのか。 AIを駆使してトラックを作るような、新手のタイプの音屋が今後出てくるだろうか。それにしても絶対数はかなり減るだろう。生産効率が違いすぎる。
私というか、ウチはそっち関係に今後も深入りすることはなさそう。 効率や品質は認めつつも、私のやりたいことはそういう工業製品としての音楽制作ではないからだ。 私は音楽作品を作るのが楽しい。楽しいことにしか興味が無い。


- 10/3
スーパーカセットビジョンの音源部(uPD1771C)を再現したというプラグインシンセが存在することを、ごく最近知った。 知らなかったというか、その辺りに全く調べを入れていなかった。
以前SID音源の完全再現を謳うプラグインシンセがあったのだが、期待外れだったという経験があった。 ファミコン音源系のプラグインとかも、納得行った試しがない。 音の再現度が低いというより、私の求める何かを持っていない。 これは音ではないのかもしれない。
例えば音源チップの発する音を完璧にサンプリングしたとして、単音だけ聞けば区別が付かないかもしれないが、曲を作るとなると発音メカニズムの違いはきっと響いてくる。 私はサンプリング技術にケチを付けているわけではない(波形メモリー音源とサンプリング音源に技術的垣根はない)のだが、求める何かを具備していないことだけは、聴けば感覚的に分かってしまう。
上記のプラグイン、試用版を入れてみたのだが、予想通り。 スーパーカセットビジョン音源系のプリセットを聴いてみたのだが、実にギミックフル・派手で、正直「どこがスーパーカセットビジョンだよ」と思ってしまった。多分あの音で作った曲を聞かせて、スーパーカセットビジョンを想起・懐古する人は絶無だろう。
再現精度が甘いわけではないのだろう(余計なものを加え過ぎているきらいは感じるが)。むしろ、下手に音源の持つポテンシャルを最大限活かし過ぎて、プリセットの音がリアルタイムのスーパーカセットビジョンのソフトで使われていた音・音楽とかけ離れてしまっているのではないか。 良い悪いの話ではなく、私の求める何かが存在していない。